お店の電話番号をコピー

アカリ(21)
T164 B88(E) W56 H87
投稿日時

山の麓に伝家の宝刀ならぬ
フルアーマーで参じた私の視界は
一瞬にして絶望という名の霧に包まれた。
眼前に山神様が踏み荒らした跡かのように
緑が溢れかえっている。
ジャージ。
ジャージ。
ジャージ。
どこまでも均一化されたダイダラボッチが
手足を投げ出して、その見えない身体が
どこまでも広がっている。
殉職。散華。
私は自由の忠実な下部として
模範的な行動を示しただけであるのに
戦地に身を投じる前に敗残兵と成り果てた。
同時に、私の中の現実主義者が
厳しく私を責め立て始めた。
そもそも、自由の忠実な下部とは何ぞや。
自由に飼い殺しにされてるじゃないか。
阿呆め。ハナから本末転倒じゃないか。
云々。
しおりに「可」と書かれていたはずの私服は
たった数名しかいなかった。
そして、私のような極彩色を提示する
殉教者は皆無だった。
自由は死んだ。
板垣が死んだから自由も死んだのだ。
だとしたら、随分前から
自由は死んでいたのだなぁ。
嗚呼、私は野に咲く曼殊沙華。
所詮一輪の花に過ぎぬのでございますから
どうぞ皆さまお気遣いなく。
目先の珍妙なるに目を奪われて
ご自分の脚元がお留守になっては
危のうございますからね。
さあさあ、どうぞ私のことなど
うっちゃってくださいまし。
場違いな異物感を
必殺の私服より色濃く醸し出しながら
私は出来るだけ小さくなって
朋友たちの視線に平身低頭
愛想嘆願しながら歩いた。
だが、全体主義の権化である
教師という名の悪魔が
作成したカリキュラムは
尚も悉く私を苛み続けた。
チームごとの写真撮影という儀式。
シャッターの音を合図に
恥辱の鉄槌が振り下ろされる。
緑緑と生い茂る草の中に際立つ棕櫚。
一人、燦然と輝くわたくし率。
シラフの太陽は馬鹿馬鹿しいまでに輝いて
嫌がらせに私に
スポットライトを当てているようだ。
高いところであんなにも自己主張している
不届き者に「目立たされている」私。
なんという理不尽。
皆、見るならば頭上で能天気に
熱を振り撒いている
目立ちたがり屋のアイツに
目を向けてしまえばいいものを
目が眩むのが嫌だからといって
それは御免被る様子。
やーい太陽め。ざまあみろ。
行き過ぎた自己顕示欲に人は閉口するのだ。
目も当てられないと陰に目線を逸らすのだ。
そしてその視線は
根が陰でできている私に降り注いで
さらに私の後ろに影を作っていく。
冗談じゃないぞ、君。
写真が現像され
学校の廊下に貼り出された。
私は全ての使徒の罪を背負い
磔にされたキリストの気持ちに連帯した。
ジャージの波の中に
ぽつねんと遠く浮いている富士。
葛飾北斎の捉えた
奇跡の一瞬の中に見る寂寞。
「孤高」から「高」を括った虚飾を取り除けば
「孤独」になるのであろうか。
更にそこから「孤=個」を取り去ったら
ただの「毒」になったりするのかしら。
私の「自我」が具現化したそれは
「過ち」の決定的証拠として
学び舎に展示され続けた。
これは、罠だ。
この学校というシステムが
私をまんまと落とし穴にハメたのだ。
でなければ
なんだって中途半端に統一もせず
「私服でも可」などという
ネズミ捕りのような選択肢を設けたのか。
私は、自らの見栄や浅はかさを
とりあえず棚にあげて
学校という巨悪に
問いを投げかけることにした。
かくも美とは、孤独である。
愚かな美は、ただ笑い者になるだけである。
しかし、これこそが
我が闘争の歴史であるのかもしれない。
災いも笑いも転じて福となること
世に儘あるではないか。
私の孤高は
死後、評価されるかもしれないじゃないか。
嗚呼、私はゴッホになりたい。
そう思いながら、私は耳の代わりに
今日も恥辱を削ぎ落す。
自我が擦り減らないように。
誰にも気づかれないように。秘密に。
ひょっとしたら
私すら気づいていないかもしれない。
嗚呼、ゴッホになりたいものだなぁ。
?アカリ?
※公式LINEが凍結されてしまいましたので
お手数をおかけいたしまして
恐縮ではございますが
再登録をお願いいたします。
※9月後半はお休みいたします。

投稿日時

――咲いたがゆえに
誰よりも赤裸にされてしまう花がある。
全く山のヤツときたらすっかり澄まし顔で
ムードまですかしてて気に入らない。
ところどころに背伸びした杉の梢が
びゅうびゅう風に吹かれて
ああもうこんなに揺らされるなら
身長伸ばさなきゃよかった、と叫んでいる。
難儀なものよなぁ。
目立ちたがりが過ぎるからそうなるのだよ。
ついでに私の悩みもこいつ
引き受けてくれないかしら。
何たって私は今心が重い。
いや、重いというか、沈んでいる。
それも、太陽のような沈み方ではない。
そもそも太陽のヤツなんてのは
どうせ半日後には何食わぬ顔で
酔っぱらったような朝帰りの赤ら顔を
禿げ頭に射返して
煩い光で人を叩き起こす癖に
沈むときもこれ
いちいちネチネチと寂しがって酒を煽り
呑まなきゃやってられんよと
赤ら顔で星々の経営する
夜の飲み屋街に消えていくのだ。
かまってちゃんにも程がある。
なんという厚顔無恥か。恥を知れ。
私はお日様に怒った。
もっと君は、慎ましさを持った方がいいな。
いや、別に
月のようになさいとかではないよ。
月なんてあいつ
あんたの光で夜を我が物顔にしてさ
それでおいて
いや自分はそんなに照らしませんから。
人様の足元を薄ら照らす程度の
役に立たない丁稚でございますから。
でもほら
そんな奥ゆかしさが美しいでしょう。
どうぞ詩に詠んでもいいんですよ。
なんて気取っている。
全く図々しい。破廉恥だ。
月の面の皮は鉄でできているのかしら。
鉄面皮ってやつ。
一人仮面舞踏会。
私は月を軽蔑した。
次から月ではなく
鉄子とでも呼んでやろうと思った。
私の沈み方といえば、鉄というよりは鉛。
そう、恥辱と後悔を体に塗りたくって
煮えた窯でじっくりコトコト煮込んで
どんどん固まっていく鉛。
ひとたび湾に投棄されたら
もう浮上できないんじゃないかしら。
カチカチ山で兎に挑んだ私の船は
泥どころか
そんな風な鉛で出来ていたのだ。
なんだって人は他人の目が
こんなに気になるのか。
私は人目が痒くてしょうがない。
あれはそう
学び舎を飛び出ての、屋外活動ってやつ。
学年生徒が一様に
息苦しい校舎から這い出て
肺臓の中身を
山の空気と入れ替えましょうって
束の間に与えられる自由と革命。
我々は自然と対峙する
独立戦争の解放軍として
目をランランに輝かせながら
外路に足並みを揃えて軍靴を鳴らす。
否、軍靴といっても
事前に配られたしおりには
「服装はジャージ、あるいは私服でも可」
と書いてあった。
既定の軍服を強制される
従軍ではなかったのだ。
やはりそこは自由解放軍。
偉大なる凱歌をあげるための大いなる一歩。
そこにも選択の自由がある。
その頃の私は、言うなれば
「おしゃれ病」に罹患していた。
オレンジと白のボーダーのシャツ。
真っ青なズボン
やけに目立つ派手なスニーカー。
これが必殺の一張羅。
今思えばあれは
一張羅なんて殊勝な言葉で飾るには
あまりにも派手過ぎた。
あまりにも過剰だった。
まるで舞台衣装だった。
だが私はそれを誇らしげに
クローゼットに掲げていた。
うっとりと眺めては悦に入り
それだけでは飽き足りず
兎角、人に見せたくてたまらなかった。
行軍においては確かに
ジャージに一日の長がある。
しかし、果たしてそれでよいのか。
自由解放軍を名乗りながら
統一規格の軍服を身に纏い
無個性の塊となるなどと
そんなことでは
自由の使徒として失格ではないか。
私が誰に相談するでもなく選び抜いた
この美しき孤高の私服。
自由とは、各々の孤高を解放し
個の解放区を打ち立て
独立を宣言することだ。
ならば私がその先陣を切ろう。
…私はあの時、孤高なる言葉に浮かれず
冷静に判断を打ち立てるべきだったのだ。
半端な孤高は、気高さを蔑ろにして
愚かな独断に堕ちるということを。
?アカリ?
※公式LINEが凍結されてしまいましたので
お手数をおかけいたしまして
恐縮ではございますが
再登録をお願いいたします。
※9月後半はお休みいたします。
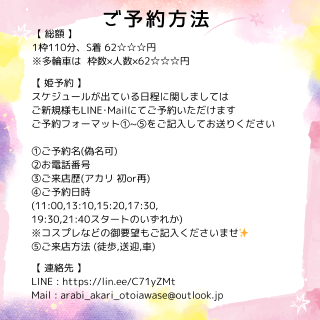
投稿日時

「あ、そうだ。あんたたち」
ママがふと思い出したように
カウンター下をごそごそ探り出した。
「これ、着てみる?」
出て来たのは、色褪せた浴衣。
洗濯のりも抜けきったような布地だが
妙に艶めかしい。
「着る着る!それママのお古なの?」
「そうよ、あんたこれ、特別よ」
クロ子はノリノリである。
「お姉さんたち、はいはい順番ね。
写真撮ってあげるから」
真っ先に袖を通したクロ子が
「似合う?」と回転してみせる。
「似合う似合う。
銀幕スターの2号さんみたい」
「2号って何?仮面ライダー?」
「あんた馬鹿ねぇ、愛人よ愛人」
「ダメじゃん!」
クロ子はまたケタケタと笑う。
ママはそんなクロ子にまた乾杯する。
「ほらアカリも早く着てみなって」
クロ子に半ば無理やり薦められながら
私も観念して羽織ってみた。
案外着心地が良い。
「あら、あんたなかなか色気あるじゃない。
これは1号さんね」
「納得いかない!」
クロ子が赤ら顔で抗議している。
まだ大して呑んでいないのに
すっかりできあがっている。
そう、彼女は酒好きのくせに
滅法アルコールに弱いのだ。
下手の横好きとでも言おうか。
いや、なんか違う気もする。
なんだか私も酔ってきたような。
「1号って正妻ってことですか?
私の勝ちってことですよね?」
「あんた馬鹿ねぇ
1号は泣かされるのよ。可哀想に」
「何号が正解なんですか!」
クロ子は大爆笑だ。
ママはまたも、涙に乾杯
とか言って杯を仰いでいる。
写真を撮り合い
一通りキャッキャと浮かれ騒ぎ
ともあれここはまだほんの
二件目であることを思い出した。
呑み歩きの序盤で潰れては元も子もない。
「そろそろ出ようか?」
充分楽しんだし
ということで私たちは腰を浮かせ
会計を頼んだ。
しかし、伝票を見た
私の視界は一瞬グラつき
ほんのり赤みを帯びていたはずの頬は
一瞬にして病的な青に変わった。
二万三千四百五十円。
お通しの枝豆とカクテル2杯ずつ。
たったそれだけで、である。
やはり一件目の酒に
マジックマッシュルームでも
入っていたのか。キノコに乾杯。
しかし、何度まばたきしても
目の前の数字は揺らがない。
2万。…2万!?
クロ子は「へぇ」と笑っている。
ママは紅い唇の端を上げ
何でもないと言った風に
「カードも使えるわよ」と告げる。
私は観念した。
ここで払わなければ
きっとフィリピンかバングラディッシュ
辺りに売り飛ばされてしまう。
移民問題が取り沙汰されている昨今
我々までがいち早くエスケープして
移民と化しては
我が国に申し訳が立たない。
何より、そんなことになれば時を置かずして
霊界の移民になる可能性が高い。
やんぬるかな。
財布から諭吉を引き抜く手が震えた。
いや、栄吉だった。
なんだか余計に腹が立った。
くそぅ、諭吉を返せ!
二重の意味で、そう思った。
外に出ると、浅草の夜風が妙に冷たい。
スマホで店名を検索すると
案の定「ぼったくり注意!」
の文字が踊っている。
なるほど。
他の客がやけに大人しかったのも道理だ。
どうやら、ママがしれっと口にした酒代が
すべてこちら持ちだったらしい。
道理でことある毎に
乾杯乾杯と囀っていたわけだ。
あの厚化粧に食わせるカクテル代を
私が背負わねばならないとは
なんたる不条理か。
離島出の蛮勇娘・クロ子の誘いに
盲従した報いが、これである。
私は腹が立ってきた。
よっぽど、彼女を責めようとした。
無鉄砲も大概にしろと。
が
同時に自身の主体性の無さにも辟易した。
指示待ち人間、道なき道を行く。
とどのつまり、これはおあいこなのである。
おかまの話は確かに面白かった。
だが、金が絡むと笑いは霧散する。
人間とはかくも不均衡な存在か。
良心とはなんだ。
私は無理やり、自分に言い訳をした。
あれはチップだ。
私たちこそ、あの悪辣な守銭奴に
良心をくれてやったのだ。
世知辛い世間を渡るため
私は度々、良心という不定形な概念に
折り合いをつけてお茶を濁す。
クロ子はといえば
「楽しかったから、まあいいじゃん」と
涼しい顔で笑っている。
その笑みが羨ましく思えた。
彼女の豪放磊落な視界から見える世界は
幸せな光で満ちているのだろうか。
私は世界に苛まれているのだろうか。
否。悩み多き優柔不断な私の世界にも
それなりに苦難という人間らしさが
満ち満ちているわけで
そこを比べてしまっては
いよいよ負けな気がした。
「どうしたの?」
「なんでもない」
それきり黙って歩きながら
なんだかんだ
私たちは良いコンビなのかもしれない。
なんてことを思いつつ
私たちの飲み屋巡りは
大して酔うこともなく幕切れとなった。
その後、私は無理にクロ子を説得し
ようやくスカイツリーに登った。
眼下に広がる街の灯火は
まるでトロイアの城砦のようで
私は悠々自適の神気分に浸り
存分にゼウスの傲慢を
味わうつもりであった。
が、青い空の端に
茜色の夕焼けが大きく迫ってくる様が
ハルマゲドンを想起させ
結局のところ「嗚呼、人生は黙示録」
などと訳のわからない感慨に沈みながら
私の姦しい休日は
静かに幕を閉じていくのであった。
?アカリ?
※公式LINEが凍結されてしまいましたので
お手数をおかけいたしまして
恐縮ではございますが
再登録をお願いいたします。
※9月後半はお休みいたします。

投稿日時

一通りグーグルマップに裏切られ
彷徨いに彷徨いつつも
私たちはなんとか
いかにも歴史のありそうな
飲み屋が肩を寄せ合って並んでいる
目的の場所に辿り着いた。
思いのほか店が乱立しているせいで
どこに入るのが正解なのか
わからなくなってきたが
コンビニの飲み物は潔く前からとる派だ。
と自慢にもならないことを
誇らしげに宣うクロ子に倣い
とりあえず賑わっている
目の前の一軒に入ることにした。
乾杯ビール。さよなら休日。
その泡の苦いこと苦いこと。
揚げたてのタランチュラを
?みちぎったような味だ。
麦の代わりにヒロポンでも
入ってるんじゃないかしら。
毒が回って周りのお客の笑い声が
蟹の断末魔に聞こえる。
頭の中まで泡だらけになりそうだ。
こんなものを飲み干した日には
脳みそが蟹味噌になってしまう。
出ようか。
言うや否やクロ子は立ち上がった。
こういう時の彼女の
衒いの無さはありがたい。
なんだかんだ私たちは
優柔不断と無鉄砲で
良い組み合わせなのかもしれない。
私は蟹味噌でそう思った。
「いや、凄いね。
あれで客商売が成り立つなんて。
人類はまだまだ多様性に満ち溢れているよ」
「多様性ってもう死語らしいよ」
「ええ?勝手に流行らせといて
代替品も置いてかずにトンズラですか?」
「ダイバーシティの時代ですから」
「小賢しい!」
横文字アレルギーなクロ子は
苛立ちを募らせた勢いで次の店に入った。
これだからリモート・アイランドの
バーバリアン・カルチャーは
スケールしない。
プリミティブなピープルには
リムジン・リベラルな
アジェンダが通じないのだ。
アーバン・エリートは
チェンジング・タイムズを
スマートにサヴァイヴし
サステナブルでインクルーシヴな
ソサエティをデザインして
いかねばならないというのに。
そしてマイ・ブレインはすっかり
ボイルド・クラブ・エッセンスと化し
コンセプトやナラティブは
フロートしてはエフェメラルな
バブルのように
ヴァニッシュしていったのだ。
…あのビールには本当に
ヒロポンが入っていたのかもしれない。
間口の狭い、まるで洗濯機置き場のような
小さなバーだった。
カウンターが数席と
ソファで囲んだボックス席がいくつか。
暗がりにピンクのネオンサインが
湿ったように滲んでいる。
ケバケバしい光を背に
ひとりが数人の客に囲まれ
陽気な笑いを振り撒いて談笑している。
多分あれがママである。
ママは黒地に赤茶けた
鶴が無数に飛び立つ刺?が施された
派手で大きな法被を羽織り
黒のショートボブに
深い紫のニット帽を浅く被っている。
やたらに騒々しいメイクと
その口調・身振り手振りからして
どうやら彼…彼女は「おかま」らしい。
「ちょっと面白そうじゃない?」
クロ子はそう囁くと
吸い込まれるようにその輪の中へ加わった。
勢い私もそれに続いて並ぶ。
「あら、あんたたち、初めましてね。観光?」
「いや、そんな大したもんじゃないです。
飲み屋を回ってるんですよ」
私たちはとりあえず
適当にカクテルを注文した。
すると「ちょっと私も」と言って
ママも同じものを
自分のグラスに注ぎ込む。
乾杯カクテル。さよなら性別。
「そんでそれが
カブトムシを煮込んだ味がして。
もうゲロゲロでしたよ」
「あんたダメよ
この辺の安酒は混ぜ物だらけなんだから」
「一体、何が混ざってるって言うんです?」
「そんなこと言えないわよ。
界隈から追放されちゃうわ」
「え~?ママはもう生物学上からも
追放されてるんだから怖いものなしじゃん」
「あら、言うじゃないあんた。
もう私飲んじゃうわよ、乾杯」
クロ子とママは意外にも会話が弾み
ママはノリノリで自分の杯を
空にしては満たし、満たしては空けていく。
その喉仏を上下させながらの
豪快な飲みっぷりは
まるで食堂が太い血管に
変わったかのように脈打ち
ゴクリゴクリというより
ドックンドックンといった感じの
オノマトペが聞こえてきそう。
顔は暗い照明にぼんやりとしていて
赤いのやら青いのやら区別がつかないが
どうやらママはザルのようだ。
私は瘤取り爺さんの宴会鬼を
ママのうるさい化粧顔に重ねてみた。
かなりお似合いな気がした。
「やっぱりヒロポンとか
入ってたんですかね?」
「まあ、あんた大人しそうな顔して
突拍子もないこと言うわね。
もう飲むしかないじゃない。乾杯」
「だってあの後
ちょっと言語中枢に
異常をきたしたような気がしたんですよ」
「あんた、そりゃマジックマッシュルームよ。
キノコに乾杯ね。乾杯」
なんだかんだで
私もそこそこ楽しくなってきた。
ママはことあるごとに乾杯を繰り返し
調子よく笑い
勝手に身の上話を繰り広げては
涙目になったりと忙しかった。
「あの人はねぇ、良い男だったのよ。
アタシはそれからプリテンダー歌うたびに
涙が止まらなくてねぇ。
もう飲むしかないわよ。乾杯」
クロ子は案外こういうのが楽しいらしく
肩を揺らしてケタケタと笑っている。
かくいう私も、誰かと他愛もないことで
談笑するという行為は好物なものだから
この空間が割に心地よく感じられた。
?アカリ?
※公式LINEが凍結されてしまいましたので
お手数をおかけいたしまして
恐縮ではございますが
再登録をお願いいたします。
※9月後半はお休みいたします。


投稿日時

世界の終わりを
小銭で前払いする作法である。
「昼間から酒が飲めるんだって」
クロ子が気焔をあげている。
昼間から意識を酩酊させて
前後不覚を望むとは
何という不埒ものであろう。
そもそも、休日にとりあえず
浅草駅で待ち合わせをしてから
ブラブラしようという約束に
30分も遅刻しておきながら
第一声がこれである。
大方この大雑把な友人のことであるから
目覚まし時計も掛けずに寝た横着の報復を
いつも通り受けたに違いない。
仕事には一度も
遅刻をしたことがないと豪語する癖に
私との約束を
その外に置いて反故にするとは
全体どういう了見であろうか。
私と仕事どっちが大事なのよ!
という古からの伝家の宝刀の柄が
喉元まで出かかったが
返す刀で仕事と答えられる可能性も
往々にしてあるのであって
そうなってはこちら矢も楯も堪らず
そのまま絶縁と相成る未来も
想像に難くはない。
仕方がない。腐っても友情。
もし友情をバナナとするならば
腐りかけが一番美味しいともいえる。
私は、この腐れ縁の道の先に
ひょっとしたらうまい話が転がっているのを
見つけるかもしれない
という秘めたる打算を
頭の中で少しく弾いてから
雑技団よろしく宝刀の柄を
元の胃の中に収めた。
しかし聞けばこの女、夕べも遅くまで
会社の付き合いで飲み過ぎたために
この不祥事をしでかしたとのことである。
であるならば、何故に重ねて酒を呑もう
などという発想が出てくるのであろうか。
昼間から?んで?まれて呑まれて呑んで
微睡み、目を開けると見知らぬ天井。
ぐるり見れば、そこは寂れた倉庫。
半裸に剥かれたクロ子の両手両足は
安っぽい手術台に固定され
周りにはどう見てもカタギではない男たちが
不穏な笑みを浮かべている。
その間を縫って腰の曲がった初老の小男が
キャスター付きのテーブルを
押しながら現れる。
テーブルの上には赤茶けたサビの浮いた
不衛生そうな鋏やメスがズラリ。
クロ子は漸く己の置かれた状況を悟る。
なんということか。
酩酊の末に路肩に酔い潰れ
そこに通りかかって
自分の介抱を引き受けたあの紳士が
実は臓器売買の闇屋だったなんて。
そういえば、アカリは一体どうしたんだ?
友人のかかる異常事態を鑑みて警察を頼り
今まさに直談判を終えて助けをこちらに
寄こしている最中であろうか?
いや、あの薄情者のことだ。
さては、酔いつぶれた私を
よりによってこんな治安の悪い
浅草の路地裏にほっぽり出して
お一人様でご帰宅しやがったに違いない。
許すまじき外道だ。
畜生の人非人め。
こうなったら末代まで祟ってやる。
例え私の臓腑が世界を駆け巡ろうと
恨みを宿した腎臓・肝臓が
移植者の意識を乗っ取り
必ずあの裏切り者を追い詰めるだろう。
そして無情にも夜の刻は
犠牲の嘆きを嘲笑うかの如く過ぎ去り
クロ子の呪詛は倉庫を覆う
黒い靄と一体になって黄泉を流転。
一回りして浮世に辿りついたその怨念は
虚大霊となって
竜の口、獣の口、偽予言者の口から
三つの汚れた霊として顕現。
それらはアカリを見つけるや否や
あっという間にかっ攫い、憐れ彼女は
ハルマゲドンという巨大な厄災の中に
呑み込まれ消えてしまった。
アカリの行方は、誰も知らない。
なんてことだ。
話が黙示録にまで発展してしまった。
ええい、ヨハネ黙示録十六章のことなど
誰が信じるものか。
ともかくクロ子は想像力が足りないのだ。
かかる事件の待ち伏せの可能性を
露とも考えず
泥酔に泥酔を重ねようとは、何たる暗愚か。
離島生まれのこの女は、所詮
本土の土を踏むようにはできていないのだ。
そういえば、彼女の父親というのも
聞くところによると
津波にサーフボードを持ち出すような
向こう見ずの蛮族だったではないか。
クロ子も親譲りの無鉄砲で
子供のころから
損ばかりしているに違いない。
全くとんだ坊ちゃんである。
二階から飛び降りて
腰を抜かす方がまだしも健全だ。
「仲見世通りでお酒片手に
食べ歩きでもいいんじゃないの?」
「それじゃ飲みって感じがしないじゃん。
日中の酒場の雰囲気がいいんじゃん」
彼女は尻を落ち着けて飲むことに拘り
一向に譲らない。
どうやら、そうすることで
社会から這放たれた背徳感を
より一層堪能できるという腹積もりらしい。
私は呆れ果てた。
そんなインスタントなアナーキズムのために
どうして肝臓と休日を
潰さなければならないのか。
しかも彼女の示す酒場は
仲見世通りから大きく外れたところにある。
わざわざ浅草まで来たのにも関わらず
どうしてそんな
僻地まで行かねばならないのか。
それより私は、スカイツリーに登って
アリのような人込みを眼下に据えて
トロイアを見下ろす
ゼウスの気分など味わいたかったのに
クロ子は全く取り合わず
気付けば通りを外れて
裏路地をズンズン進んで行った。
やんぬるかな、私は観念して
偽予言者候補の後を追いかけた。
?アカリ?
※公式LINEが凍結されてしまいましたので
お手数をおかけいたしまして
恐縮ではございますが
再登録をお願いいたします。
※9月後半はお休みいたします。
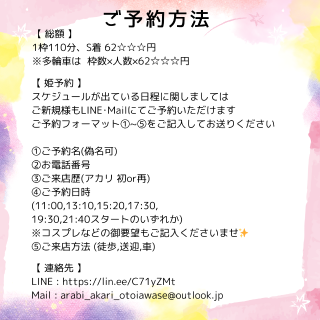
投稿日時

そしてついに、順番が回ってきた。
遠くから眺めるのに
飽き飽きしていたはずのパーテーションは
間近に寄ると
生々しい時間の風を心にふき込んできた。
緊張が血中のヘモグロビンひとつひとつに
伝導して全身に行き渡る感覚がした。
心臓の鼓動がピッピッピッピッ
っと速くなりすぎて
もはや音が繋がってピー
…とご臨終しそうだった。
前職でタレントに対しては
耐性がついているものだと思っていたが
どうも推しというものは
そんなことに関係ないらしい。
生れて初めて感じる逢瀬の胎動に
身体を強張らせつつ
パーテーションの中に歩を進めた。
仕切りの中の狭い空間は
白く発光していた。
勿論、どこにも
特別な光源なんてなかったのだが
新しい光が広がっているような心地がした。
その中心にある
テーブルを隔てた目の前に、彼女はいた。
少し幼さを残しつつも美しい顔立ち。
陰りも屈託もない笑顔。
小柄でスレンダーな体躯は
会場中の光を集めた中から飛び出して
まるで空気をくり抜いたかのような
くっきりとした輪郭を描いていた。
「わあっ!女の人やぁ!
嬉しい~!ありがとう!」
会った瞬間に、彼女の顔は
久方ぶりの親友と再会したかのように
パッっと明るく開いた。
「初めましてですよね?
どこで私のこと知ってくれたんですか?」
「エッ、アノッ、ワタシ
イツモドウガデ、ミテマシタ」
余りの眩しいオーラに
私は影ごと小さく縮んでいきそうだった。
彼女は更に目を輝かせた。
「うわあ!なんや恥ずかしいなぁ~!
でもアレで知ってくれた方も多くて!
ありがたいですホンマに!」
キラキラした瞳が
真っ直ぐ私の眉間を的確に射抜いてくる。
「アノ、キョウ、ワタシ
コウイウノクルノハジメテデ
キンチョウシマスネ」
「ええ!ホンマですか?
うわ~!嬉しいなぁ!
ほんなら気合入れてサイン書きますからね!」
丁寧にイラストを添えて
カレンダーに可愛らしいサインを描く彼女は
その姿からさえ一生懸命さが伝わってくる。
「…ハイッ!どうですか?」
「スゴクカワイイデス」
「良かった~!」
その後、私は一通り
動画を通してとても感動しただのなんだのと
お気持ち表明を一通り伝えた。
彼女はそれに逐一
これまた感動の籠った
リアクションで返してくれた。
「じゃあじゃあ!チェキ撮りましょ!
どんなポーズがいいですか?」
「ア、エエト、ナンカ、ドウシマショウ?」
「じゃあ、二人でハート作りましょう!」
彼女は自然に私の隣に並び
蝮の顎の形にした
左手を私に差し出してきた。
唐突な接近に私は
身体の前側の体積が粒子に削られて
影の中に逃げ込んでいく気がした。
そして
ぎこちなく大福を掴むような形の右手を
蝮の顎に合わせた。
なんだか右肩上がりなハートが出来た。
シャッターが切られる瞬間
私はカチコチの表情筋を
無理やりに吊り上げた。
「ホントに来てくれてありがとう!
今日ホンマに会えて嬉しかったです!」
私は最期まで平身低頭の体であった。
彼女と空間を同じくした時から
その輝きに圧倒されっぱなしだった。
しかして私は
なんだか明日の活力に満ちていた。
これが推し活の効果だろうか。
彼女は終始笑顔で目を見て
凄く心から向き合って、壁なく喋りかけて
元気を与えてくれた。
そして彼女もまた
自分のためにここまで足を運んでくれた
ファンに心から感激し、元気を増していた。
なんと健やかな永久機関であろうか。
チェキを見ると、夏の光のような笑顔と
波打ち際の巌のような笑顔が並んでいた。
あの場の空気そのものを
残酷なまでに切り取った
かのような写真だった。
推しは、会いに行く前と後で
印象は何も変わらなかった。
天然自然、和顔愛語、温厚篤実
でもただの女の子で。
それが、とても嬉しかった。
本当にあんな子がいるなんてことが驚嘆だった。
そして、チェキを見ては
なんだか心に穴が空いたような気分になる。
また推しに会いに行った時は
次こそシャンとした姿で
チェキを撮れますように。
願いながら
チェキを片手にドーナッツを食べている。
この甘い甘い外枠を食べ尽くしたら
心にぽっかり空いた穴もなくなるだろうか。
そんなことを適当に思いながら。
?アカリ?
※公式LINEが凍結されてしまいましたので
お手数をおかけいたしまして
恐縮ではございますが
再登録をお願いいたします。
※9月後半はお休みいたします。

投稿日時

――推しという名の栄養素は
恥と感激とドーナツの味がした
私にも所謂、推しというものがいる。
どせいさんではない。
霊長類の女の子である。
あるYOUTUBEの企画から
一気に有名になったその子は
思いやりの権化だった。
容姿端麗にして純粋無垢。
人一倍に不器用なれど
目の前の不幸を決して放っておけない。
例え身体が震え、涙が流れようと
他人に降りかかる理不尽には
真っ向から立ち向かう。
自分のこととなると自信がなく臆病なのに
周りのこととなると瞬時に菩薩の面が顕れ
ひたすら地母神の如く化す。
そこには自己保身も承認欲求もない。
苦しんでいる人がいたならば
己のことなど形振り構わず
いつも全力で救済に努めるのである。
共感と、献身と、抱擁。
自分にできることは全部やって
それで足りなければ
勇気を奮って迷わずその先へ足を踏み出す。
穢れなき思念。不純物なき波動の螺旋。
それは
自己犠牲と隣人愛と他者貢献の混合物。
彼女を天使と呼ばずして何と呼ぼう。
私は決してミーハーではなく
むしろ芸能人に対して、人一倍に憧れなど
持ち合わせない人種だと思っていた。
それは、音響時代
数々の芸能人に不遜な態度を
とられた経験からもきているのだろう。
楽屋裏で作られた
イメージの仮面を抜いたアイドルは
大多数がふてぶてしく
傲慢で、高飛車だった。
しかしながら、脆さと強さが
紙一重に同居する彼女は
画面越しにも関わらず、その紙の隙間に
すっかり私の心を
閉じ込めてしまったのである。
そんな稀有な性質が
世間に見つかってからというもの
彼女の人気はどんどん急上昇。
私もその人気に引き寄せられた
一人ではあるものの、彼女の笑顔が
スポットライトの形をした
ヤスリで削られていかないか
少し心配でもあった。
そう思うと、どうにも会ってみたくなった。
すると、間もなく催される
レースクイーンのサイン会に
彼女の名前があった。
急に爆発的に存在を
世に放った彼女であったが
その時は、まだメインの仕事が
レースクイーンに留まっている
過渡期の狭間だったのだ。
ここで行かねば、永遠に会えない気がした。
根が人見知りの私ではあるが
かくして腹を決め
初めての推し活に挑むことと相成った。
渋谷で開かれたサイン会場は
男性でごった返していた。
数える程度にチラホラ見える
私のような女性ファンは
場違いであるかのように浮いていた。
人生最初の推し活の
いきなりのハードルの高さに
私は気圧されていた。
できればハードルの下をどさくさに紛れて
忍者走りで潜っていきたいような心持ちで
列の中に気配を消していた。
会場はパーテーションで
三つのブースに分けられ
三人のレースクイーンが
並列にファンと交流する形であった。
推しのブースは真ん中にあった。
そしてそこのパーテーションだけ
分厚く仕切られて
推しの姿だけが遮られて見えなかった。
両脇のレースクイーンの子たちは
申し訳程度の壁しか設置されておらず
列の中からでもその姿が確認できた。
そして膨大なファンの列は
そのほとんどが中央に吸い込まれていった。
左右に行く者は
10人にひとりあればいい方であった。
芸能界においての、知名度という力の差が
容赦ない格差として眼前に展開されていた。
どうしたって愉快な顔には
なれないであろう左右の子たちは
それでも少ないファンが目の前に来ると
満面の笑みと黄色い声で
本当に嬉しそうに向き合っていた。
そんな彼女たちの姿を見ていると
私の心には変な靄がかかり
寂しい気持ちになった。
景色が寒色を帯びて見えた。
推しに会いに来たはずなのに
いつしか彼女たちを
応援したい気持ちが強くなっていた。
がんばれ。貴女たちはとても素敵だ。
長蛇の列の中で
私は自分が一体誰のファンなのか
なんだかわからない感じになっていた。
が、姿の見えない推しのブースからは
左右よりも一層
黄色い大きな声が絶えず響いていた。
途方もない人数と触れあいながらも
推しの声には一切
疲れも雑念も混じっていない。
毎回、新鮮に感激している様子が
壁越しに伝わって来た。
一時間近く
気まずさを感じながら並んでいる中で
推しのテンションだけは
全く落ちることがなかった。
一体どういう体力をしているのだろうか。
精神が体力を凌駕している?
それにしたって
精神にも体力はあるはずだ。
だとするとこれは
感情が精神をも凌駕しているのだろうか。
そんな人間が本当に存在するのだろうか。
これだけの人数を裁くのには
如何に人間愛が強い子であろうとも
どこかで定型な対応に
ならざるを得ないのが定石である。
しかし、漏れ聞こえる推しの会話の中には
ひとつたりと予定調和な文句がなかった。
微塵のおざなりもなかった。
メディアでの彼女の像が
ある程度は作られたものであることも
覚悟してきたのだが
耳には全くそんなことは
ないように聞こえた。
?アカリ?
<a data-mce-href="https://x.com/akariakarinan" href="https://x.com/akariakarinan">X</a>
<a data-mce-href="https://lin.ee/C71yZMt" href="https://lin.ee/C71yZMt">*???????*公式LINE</a>
??<a data-mce-href="mailto:arabi_akari_otoiawase@outlook.jp" href="mailto:arabi_akari_otoiawase@outlook.jp">arabi_akari_otoiawase@outlook.jp</a>
<a data-mce-href="https://lit.link/ARABIakaridada" href="https://lit.link/ARABIakaridada">ご予約詳細は?</a>
※公式LINEが凍結されてしまいましたので
お手数をおかけいたしまして
恐縮ではございますが
再登録をお願いいたします。
※9月後半はお休みいたします。

投稿日時

剥き出しの木の匂いが濃く漂う店だった。
先に着いてしまった私は
席に尻を下ろして
いち早く木との一体化を試みていた。
そして木目が腰辺りまで
せり上がってきたような、そのぐらい。
階段を上がってくる女性の姿が見えた。
一目でリカだと、すぐにわかった。
彼女はいわゆる丸の内系OL
といった装いで、清潔感のある
ジャケットに淡い色のブラウス。
アイコンの横顔よりも
落ち着いた大人びた雰囲気だった。
「はじめまして」
着座の前に笑顔で挨拶する彼女に
私は木にはった根を
引っこ抜いて礼を返した。
彼女はメニューも見ずにコーヒーを頼むと
おもむろにバッグからスマホを取り出した。
電子書籍派なのかしら?
「ねえ、この子見てほしいんだけど」
新しく発掘した新人作家だろうか?
スマホに目を落とす。
フリフリの衣装。戦隊モノのような色合い。
無数のサイリウムの残像が
原色の照明に集る月光蛾のように
狭いキャパを埋めている。
これは、地下アイドル、というやつだ。
しかも彼女ら、韓国語である。
日本のアニソンなどカバーしている。
とんでもなくしんどいことが
起ころうとしている。
地下アイドルだけでも
全く守備範囲外なのに
そこに韓国という異文化まで加わっては
もはやUMAだ。
「ああ…」と私が呻吟を漏らすよりも早く
リカは二倍速で語り始めた。
「顔が骨格レベルで美しいの。
ステージングも天才的で
特に2番のBメロが…」
話はMCの構成、衣装の変遷
ファンアートのクオリティ
海外ライブでの神対応
更には推しとブリトニー・スピアーズの
比較検証に至るまで…
洪水のように話は続いた。
私はサムギョプサルとチャプチェの
ひつまぶしを味噌田楽で固めて
納豆味噌と共にチゲ鍋で
煮込んだものを見るような虚ろな目で
その声を聞いていた。
何度か我に返り、乾坤一擲の合間を縫って
文壇の話を差し込もうとも試みた。
「芥川賞と直木賞が
両方該当作なかったのって
最近求められてる作風が――」
「ああ、そういうこともあるよね。
で、こっちがブリトニーの
発声時の周波数なんだけど
推しと比べて――」
焼け石に水。台風にポメラニアン。
投げた話題は
巻き上げられて二度と帰ってこなかった。
そして私はまた元の暴風雨に
ライフラインもなしで晒された。
そして2時間後「やっと話せてよかった!」
彼女は満足げにそう言うと
この後、ファンミがあるから!
と言って、足早に席を立って店を後にした。
取り残された私と目の前のコーヒーは
すっかり冷め切っていた。
耳の奥に薄くこびりついた
チゲ鍋アイドルの歌が
微かに鼓膜にリフレインしている。
…あの文通での彼女は
果たして誰だったのだろう?
幻?ゴースト?ニューヨークの?
あの、デミ・ムーアがろくろ廻してるやつ?
マッチョが後ろから
抱き着いてくるシーンと共に
ライチャス・ブラザーズの
名曲が脳裏に蘇った。
それは雑音を優しく拭って
緩やかに聴覚を浄化してくれた。
しかし、文字と言葉で
こんなにも人格が二分化するものだろうか?
いや、私も
人のことは言えないのだけれども。
それにしたって、これはもう
ジキルとハイドではないか。
ということは、薬物?
なるほど、彼女にとって
推しは薬物なのかもしれない。
文字の中のリカは
確かな文学少女の形をしていた。
実際に会った彼女は
推し活の通り魔だった。
実像とは一体なんだろう。
人は、文字だとよく見える。
立体になると、途端にぼやける。
当然のことながら
想像の活力と、実働の活力は
全く性質が違う。
両立もできない。
が、宙ぶらりんで生きることもできない。
片方に寄っては
もう片方から責め立てられる。
これは本質的欲求と社会的仮面の
ジレンマに似ているな、と思った。
されど、私は
文字の中のリカのことが好きだった。
文字の中にしか咲かない風景も
あるのかもしれない。
文字の中でのみ完結する人間関係の美しさ。
実体を伴わない儚さ。
その冷たさ。その暖かさ。
逢瀬の薄氷を踏むまで、それは
優しさが奥深さを連れてくるように
確かな形でそこにあった。
私は帰路の雑踏のメロディーの中で
静かにアプリを消去した。
地盤を踏み抜いてしまわないように。
軽やかに。
?アカリ?
※公式LINEが凍結されてしまいましたので
お手数をおかけいたしまして
恐縮ではございますが
再登録をお願いいたします。
※9月後半はお休みいたします。

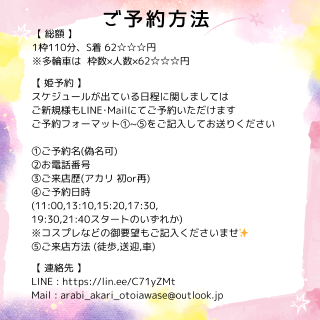
投稿日時

ケース⑤
【市政とマッチングの狭間で】
「なんか、アプリの中って
議場みたいですよね」
何言ってんだこの人?
わけのわからない比喩を繰り出すメグミは
地方議員の秘書を名乗った。
「皆それぞれの立場で『政策』という
恋愛観を出して、それに賛否を示す。
合意形成の場ですよ」
彼女は、ただ情報を遠回りさせるだけの
やたらに無駄な言い回しを好んだ。
本人的には比喩表現が
見事に上手く炸裂してご満悦なのだろう。
本当に議員秘書なのかどうか
少し疑わしくなってくる。
加えて彼女は
妙に弁が立っている風の喋り方で
やたらと「情報」に詳しそうな
雰囲気を匂わせてくる。
「この前の委員会、ほんとヤバくて。
議員が『非公開案件』を
LINEで漏らしてたの、私だけ気づいてて!」
「それが本当であれば
メグミさんは更にセキュリティ性の低い
アプリのチャットで
それを二次的に漏洩させてる
ことになりますよ」
「内緒ね!情報って、動くの。
使い方次第で人が救われるし
間違えば誰かが辞職するけど笑」
自分で語尾に笑を
付けるような話ではないが
彼女が喋ってる「情報」とやらには
ほとんど中身がないので
逆に笑で正解なのかもしれない。
具体性を装った「風味」だけで構成される
彼女のエピソードトークは
看板だけ本場だの博多だのとご立派な癖に
出汁をティーバッグでとっている
インスパイア系豚骨ラーメン屋
の匂いがした。
「市民相談のメールも
恋愛相談と構造は似てるのよ。
『水道管から変な音がします』とか
『彼氏が浮気してるかもしれません』とか。
どっちも困ってる人を
どうケアするかが大事なの」
水道と男とは
およそ流れる方向が違いますよ。
などというツッコミをする気も
もはや起きなかった。
しかし「へぇ」「そうなんですね」などと
適当な生返事を返していたことが
迂闊にも彼女のギアを
上げてしまっていたようだ。
「アカリさんと会って
じっくり市政の話をしてみたいな。
もしかして一緒に何かできる人かも」
まずい。議案も可決もされていないのに
予算だけが組まれようとしている。
「顔合わせの日程は
臨時会で可決してからにしましょうか!笑」
私はそっと通知をオフにした。
チャット履歴は
公文書として表沙汰になることなく
電子の海に沈んでいった。
…それから、だんだんと
放置しがちになってしまって
いつしかアプリ自体、開かなくなっていた。
ある晩、寝る前に、ふとした気まぐれで
久しぶりに開いてみた。
すると、未読の赤い数字が
目に飛び込んできた。
「久しぶりですね。最近読んだ本
もしよかったら話しませんか?」
送り主は、リカという女性。
丸顔で前髪を下ろした横顔のアイコン。
プロフィールには
「コーヒーと古本と猫」の一文のみ。
これまで何度かやり取りはしていたが
途中で私が放置していたため
完全に音信不通になっていた。
そんな相手から返信が来ていたことが
なんだか昔の文通のようで
一周廻って風流に感じた。
素直に、少し嬉しかった。
そして再開されたチャットは
不思議なほど滑らかだった。
私と彼女は太宰治の
ユーモアの奇才ぶりについて語り
三島由紀夫や谷崎潤一郎が
齎した影響について触れ
夏目漱石の晩年にまで話を広げた。
誰かと言葉で遊んでいる感覚を
久しぶりに味わった気がした。
「漱石の前期は
比喩も構造も一望千里の広がり
時代を超えて到達困難な
筆力の孤峰ですよね」
「わかります。
でも後期は、まるで外套を
脱いでしまったような印象じゃないですか?
病後の体力、精神力の
変化もあったんでしょうけど」
「時代性に歩調を合わせた結果
初期の孤高な美文は
影を潜めちゃいましたよね。
社会心理小説に傾いて
修辞の華やかさを自ら封印しちゃって」
「その点で言うと
三島や谷崎は上手くやりましたよね」
「そうそう、時代の文壇に
新奇な感覚と美意識を提示して
完全に時代の寵児って感じで」
「太宰治は、また別枠ですよね。
道化の天才というか
唯一無二のリズム感も併せて
ダザイズムというか」
「何より人間らしさですよね。
川端康成のこと刺すって言ったり
志賀直哉とバチバチにやりあったり」
割とマニアックなやり取りが心地よく
文学談義に咲いた花は
いつの間にか小豆色の暁を連れてきた。
彼女に会ってみたい、そう思った。
こんなに話が合うなら
直接の対話も弾むに違いない。
私は初めてアプリでアポイントを取った。
?アカリ?
<a data-mce-href="https://x.com/akariakarinan" href="https://x.com/akariakarinan">X</a>
<a data-mce-href="https://lin.ee/C71yZMt" href="https://lin.ee/C71yZMt">*???????*公式LINE</a>
??<a data-mce-href="mailto:arabi_akari_otoiawase@outlook.jp" href="mailto:arabi_akari_otoiawase@outlook.jp">arabi_akari_otoiawase@outlook.jp</a>
<a data-mce-href="https://lit.link/ARABIakaridada" href="https://lit.link/ARABIakaridada">ご予約詳細は?</a>
※公式LINEが凍結されてしまいましたので
お手数をおかけいたしまして
恐縮ではございますが
再登録をお願いいたします。
※9月後半はお休みいたします。


投稿日時

ケース②
【人生もポートフォリオ】
「出会いも資産。
運用次第で未来が変わるんだよ」
そんな文言をぶち込んできた
レイナという女性のプロフィールには
『30歳でFIRE目指してます!』
と書いてあった。
彼女はチャットの一発目から
「仮想通貨とETF、どっち派?」
と聞いてくる猛者だった。
「とりあえず、今はどっち派でもありません」
「じゃあ、ビットコインと
出会いの共通点から話そうかな。
どっちも初動が命で
感情に流されると損するんだよね」
彼女の言葉は、自分の頭の中だけで
満足して完結しているようで
あまりに俯瞰を怠って
構築されているために
他者に伝聞するための心遣いが一切ない。
つまり
何を言っているのか全くわからない。
加えて、5分おきに
経済系Youtuberのリンク
コラージュしたグラフ等が
矢継ぎ早に送られてくる。
「将来設計ってさ
誰と組むかで全然変わるよ?
人生もポートフォリオだから!」
「随分と大胆な視点をお持ちですね」
「私さ、人生のポートフォリオ組んでるの。
仕事・交友・恋愛。
どれも分散投資しないと」
「でも経済論理性に交友や恋愛を置くのって
何の発展性もなくないですか?」
「あるよ。時間も感情も投資だから」
「損得の二元論で
仕事以外の人付き合いしても
疲れるだけになりませんか?」
「人生は有限なんだから
効率的に運用するべきなんだよ」
なんともつまらない生き方に
全力で舵を切っている
ように見える彼女の船。
「恋愛にも配当ってあるんですか?」
とりあえず乗船してみる。
「もちろん。かけた時間分のリターンが
男から還ってこなかったら
すぐ損切りしないとね」
彼女の辞書に無償の愛
という言葉はないようだ。
しかし彼女が自論を
本気で語っていることだけは伝わってきた。
「アカリちゃんも、自己投資しないと。
セミナー来る? 参加費は軽くペイできる」
目の前の我が人生の含み損を
スワイプでそっと損切りした。
ケース③
【孤独と対話する自撮り】
「この光、私の孤独が話してるの」
しずくという名の彼女は
白壁の前で撮られた10枚の自撮りを
一気に送りつけてきた。
どれも微妙に角度が違うだけだった。
しかし自撮りを通して
己の孤独と対話するという
彼女の感性は面白い気がした。
確かに自撮りとは
究極の自己完結の形のひとつだ。
そこに他者が介在しなければ
なるほどそこには孤独しかあるまい。
そこに映りこんだ光を
『孤独の言葉』と表現し
それが視覚化したものだというセンスも
なんだかそんなに嫌いではない気がした。
「なんだかいい感覚ですね、こういうの」
「そうでしょ? これは『午前の孤独』で
こっちは『午後の孤独』」
ネーミングセンスには閉口した。
彼女が題を付けると途端に
写真まで陳腐になる気がしたので
辞めた方がいいと思った。
が、彼女が時間ごとに
撮影を区切っていることには
なんだかフィロソフィー
なこだわりを感じた。
「あなたも顔、撮ってみてよ。
そう、泣く直前の顔とかがいいかも」
誰が撮るんだそんなもん。
そもそも『泣く直前の顔』を撮ることに
どんな意図があるのか?
皆目見当が付かない。
「なんで泣く直前がいいの?」
「人間性のギリギリを攻めたいの。
泣いちゃったら、もう感情の奴隷だから」
なんだかそれなりに丁度よく
「ぽさ」を含んでいるように聞こえた。
それで私は
さすがに泣く直前とはいかないが
試しに一枚、自分の飾り気のない
「あるがまま」の横顔を送ってみた。
果たして私は
彼女の口をついて出るであろう
人間性を透かして
更に奥深いところに触れるような
人生の深淵を感じさせるような
そんなアーティーな一言を
暗に待ち伏せた。
一体、どんな言葉のメスで
私の自撮りを解体し
モダンな表現に昇華してくれるのか?
「うーん、明暗のバランスが悪いね」
普通に写真のダメ出しをされただけだった。
あれじゃないのか
君の仕事は、その不調和に
『なんとなくのアーティー』
を付与することではなかったのか?
明暗のバランスがキレイにとれていたら
それにこそ
『欠落を隠す技には
人の本質が宿っていない』
とかなんとか言って
大いにケチをつけるべきなんじゃないのか?
何故に私の写真に限って
写実的に扱う必要があるのか。
とても裏切られた気がした。
「今度さ、二人で撮り合おうよ。
光の中で、感情を残すの」
私は返事を返さなかった。
今は残したくない感情の方が
多い気がした。
ケース④
【北向きのベッドは運気が死ぬ】
「北向きのベッドで寝てると
対人運が枯れるよ」
ハナコはいきなり初対面で
そんなメッセージを飛ばしてきた。
「なんでですか?」
とりあえずの返事を打って送る。
それと相打ちくらいの間隔で
「間取り図ある?」
二の矢が飛んで来た。
あんまりレスポンスが早いので
スマホで適当に描いて送ると
秒で三の矢が襲来した。
フリック入力で追いつくレベルではない。
もしやこれが風水の力?
風水エンジンてやつ?
チェーンコンボ簡単に繋がるアレ?
いや私にとっては
全然簡単じゃないんだよなぁ。
頭にチョココロネを二つ付けた
蜘蛛っぽいテコンドーガールを
キタエリボイスで
サディスティックに再生していると
意識の外から風破刃の三枚刃が
上中下段を掠めてきた。
「赤いものを西側に置いて。
あと、財布は黄色禁止」
「風水ですか?
あれって科学的な根拠あるんですか?」
「それは体感」
「体感ということはハナコさんは
身体知としてそれを熟知している
ということですか?」
「シンタイチ?」
「言語知外での
身体感覚での知的経験知です。
例えばその体感を言語化できますか?」
「ゲンゴチ?」
「身体知外での
言語感覚での知的経験値です。例えば…」
『体感』という言葉を信用するには
相当の信頼がいるように思える。
でも、ハナコはどこか母性的だった。
「う~ん、確かに
私も言葉を大切にしなきゃね」
「私も、もっと体感を大事にしてみます」
それから、私の部屋の西側には
赤いキーホルダーが
今も転がっている。
?アカリ?
※公式LINEが凍結されてしまいましたので
お手数をおかけいたしまして
恐縮ではございますが
再登録をお願いいたします。
※9月後半はお休みいたします。


トップ